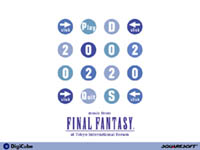| DISC1/第1部 |
| 01 |
Tuning |
オーケストラコンサートにはつきもののチューニング風景。CDにもしっかり収められ、擬似コンサート体験のような雰囲気を再現してくれているのがありがたいですよね。これがあるのとないのとでは、CDを聴く時のテンションもだいぶ違ってくるはずです。 |
| 02 |
Liberi Fatali
(Final Fantasy VIII) |
とにかくインパクトのあった「FFVIII」のオープニングムービーで流れていた楽曲です。もともと植松氏作曲&浜口氏編曲で作られた曲ですから、このコンサートの幕開けにはピッタリの選曲でしょう。基本的には原曲と大きな変化のない構成になっていますが、ド派手なドラが数箇所に加えられています。また、ケツの一音が原曲ではピアノだったのに対し、今回のコンサートではストリングスになっています。
CDを聴いていて最も気になるのは、ミックスバランスでしょう。印象を記すと、なんとなく各パートが乖離して聞こえるんですよね。コンサート会場で聴けるような一体感に乏しいというか、あまりにステレオ音場でのクロストークがなさすぎる。スネアも大きすぎて、とても通常のホールで聞くバランスではありません。
オーケストラコンサートというものは基本的にはステレオ一発録りですので、非常に難しいのです。そこは、現場のミキシングエンジニアのセンスに完全に委ねられてしまいます。逆に、ゲームで使用されているものはスタジオでのマルチトラック収録になるので、後の調整が容易ですから納得いくまで詰められますし、修正も簡単です。そういう意味ではオーケストラ録音とスタジオ録音を安易に比較することはできないのですが……と思ったら、ライナーノーツの写真を見ると、パートごとにマイク立ってますね。マルチトラック録音ではないにしろ、ワンポイントのステレオ収録ではなさそうです。
ということは、この「一体感のなさ」は、パートごとに収音されたことが原因のようです。天井にマイクを吊るしてステレオ録音したら、絶対にこうはならない。マルチマイクだと個々の調整は容易なのですが全体を捉えるのが難しく、「空気感」が伝わりにくい。アンビエンスマイクを立てたとしても個々のマイク同士の位相の干渉もあり、ベストなポイント、ベストなバランスを作るためには入念なリハーサルが必要となります。
とにかく、ただただ迫力だけを狙いすぎてしまっているミキシングで、臨場感と高揚感には欠けているのが残念です。 |
| 03 |
愛のテーマ
(Final Fantasy IV) |
スーパーファミコン時代の名曲をオーケストラで聴ける楽しみ。これぞ、FFシリーズが持っている歴史の、最大の楽しみ方ではないでしょうか。何年経っても、名曲は色褪せることがありません。
冒頭の主メロはオーボエが受け持ちます。徐々に他の楽器が加わり、厚いストリングスが愛を歌い上げていくさまは圧巻です。前の曲にあったようなやかましいリズム楽器もなく、安心して聴けるバランスですね。3分31秒からは大サビとも言える一番の盛り上がりがくるのですが、ここのラッパがかなり微妙です。流して聴いているうえではそれほど気になりませんが、ヘッドホンでじっくり聴き込んでいるとズッコケるかも。
ただし、あくまで一発録りだということを忘れずに。原則、オーケストラコンサートでの演奏ミスを指摘するのはマナー違反とされています。人間だもの、ミスもするさ。ウチはレビューサイトなので指摘しちゃってますが……。会場にいたお客が騒然とするようなミスじゃなければ、普通はスルーするもんです。なので、これ以降のレビューではミスについては触れませんのでご理解下さると幸いです。 |
| 04 |
MC-1 |
森田-ティーダ-成一と青木-ユウナ-麻由子によるオープニングMC。普通のオーケストラコンサートではMCなんて型破りですが、そこは植松氏。あくまでファンに対するサービスが大前提なんですね。堅苦しいものにはしたくないという意向もあります。
ここではFFの歴史について語ってくれています。なお、森田氏の「16年前」はライナーノーツにもあるように、「15年前」の間違いです。あっ、スルーすると言ったのにいきなりミス指摘しちゃった。 |
| 05 |
FINAL FANTASY I〜III
メドレー |
FFの歴史を音楽で振り返ろう!ということで、懐かしいファミコン時代の楽曲をメドレー形式で。プレリュードに始まり、暖かい感じの「FFIメインテーマ」、ストリングスがのびやかに歌う「マトーヤの洞窟」へ。続く「III」の「水の巫女エリア」は、もとが短い曲だけにメドレーでもコンパクトな扱い。クラリネットによる導入から、弦が寄り添うようにして盛り上げてくれます。
さらに、シリーズでおなじみの「チョコボ」はなんとも楽しげに、トランペットとピッコロが跳ねるようにメロディを奏でています。そこから、オーケストラ全体で奏でる管主体の「帝国のテーマ(FFII)」へ。スネアが勇ましく鳴り響く、大迫力のマーチになっています。
浜口氏がこのあたりの曲をアレンジするのは初めてのことだと思いますが、全体的に非常にツボをついたグーなアレンジではないかと思います。曲のオイシイところをつかむのがウマいというか。過去のFFのオーケストラCDと比べても、なんら遜色はありません。これには、大のFFファンである指揮者・竹本氏も貢献しているのでしょうね。 |
| 06 |
MC-2 |
ユウナが「光」を召喚します(笑)。FFファンにしかわからないギャグがてんこ盛りでなかなか楽しいです。CDで何度も聴くのはどうなの?という疑問もありますが、コンサート擬似体験としては正しい作りかな。 |
| 07 |
エアリスのテーマ
(Final Fantasy VII) |
これはもうハズしようがないというか、既に「リユニオントラックス」でもアレンジされた曲ですし、植松&浜口ゴールデンコンビにかかればお手のものでしょう。PS期FFの代表曲と言っても差し支えありませんね。これだけファンの思い入れがある曲だとアレンジする方も大変でしょうけど、浜口氏ならば安心してお任せできるというものです。
雄大に奏でられる序盤に対して、後半はちょっと盛り上げすぎでは?というきらいはあるものの、「Liberi
Fatali」と同じくミキシングのさじ加減もありますから、一概には言えません。なんとなくわかってきたんですが、このCDのミキシング、打楽器(スネア、シンバル、ティンパニ)が大きすぎるんではないでしょうか。そこをちょっと引っ込めるだけで、だいぶ印象変わると思うんですけど。とは言っても変えようがないですが。 |
| 08 |
Don't be Afraid
(Final Fantasy VIII) |
エアリスからガラっと変わって、「FFVIII」の戦闘曲です。原曲よりもちょっとテンポが速いです。この曲もすでにアレンジ盤「FINAL FANTASY VIII FITHOS LUSEC WECOS VINOSEC」でフルオケアレンジされていますが、そちらが原曲のシーケンスを流用して混ぜていたのに対し、今回は純粋なフルオーケストラとなっています。原曲の雰囲気を損なわないように支えているのは、意外にも右の方で鳴っているトライアングルだったりするのですから、トライアングルと言っても侮れないものです。これがあるとないとではだいぶ違いますよ。
基本的なアレンジやコーダの処理は「FITHOS LUSEC WECOS VINOSEC」と同様のものになっていますが、うねる風のようなSEが加えられていることでより混沌としたイメージになっています。あれ、そういえばこの曲に関しては打楽器のレベルが適切だな……。 |
| 09 |
ティナのテーマ
(Final Fantasy VI) |
このCDの曲の並びって、コンサートと同じですか?エアリスとティナで「Don't
be Afraid」をサンドイッチするのはいかがなもんでしょうか?まあそれはそれとして、ティナのテーマですよ。弦の刻みと木管による静かな導入から、徐々にマーチングスネア、金管が加わってきます。原曲のニュアンスを最大限に活かした好アレンジではないかと思います。やっぱ、浜口さんウマいよ!と絶賛せずにはいられません。特にこの人の弦の使い方は、個人的にはかなりツボです。 |
| 10 |
MC-3 |
演奏楽団と指揮者の紹介があります。竹本氏の話も聴けますよ。森田氏と青木嬢を見て、ティーダ&ユウナというよりはゼル&リノアだという竹本氏、かなりコアなFFファンだとお見受けいたしましたゾ。 |
| 11 |
親愛なる友へ
(Final Fantasy V) |
ギタリスト、天野清継氏を招き入れての「親愛なる友へ」。やはりこの曲にはギターは欠かせません。そのあたりこのアレンジ、「わかってるなぁ〜」という感じで納得です。あくまで主役はギターという感じで、オーケストラは控え目になっています。ギターをセンターに配置したミキシングも正解でしょう。まあステージを再現すると、こうなるべきなんですが。
天野氏は著名なギタリストでして、こうしてFF音楽に参加してもらうことは単純に嬉しいですし、ありがたいですね。ソロ名義でのアルバムも山ほど出してらっしゃるので、興味を持たれた方はぜひ聴いてみて下さい。こういった「音楽の連鎖」によって、いろいろな音楽、いろいろなアーティストに出会えるのもFF音楽の魅力だと思います。 |
| 12 |
Vamo' alla Flamenco
(Final Fantasy IX) |
やられた〜!まさかコレがくるとは予想してなかったなぁ。わかり易く言うと、「FFIX」におけるチョコボの穴掘りの曲です。フラメンコにゃギターが欠かせない!ってことで、ここでも天野氏が大活躍です。今度は負けじとばかりに、オーケストラも力強い演奏を聴かせてくれます。なんか久石譲の「ラピュタ」の劇伴みたい……。
盛り上がったところで、コンサートは第2部、CDは2枚目へ。 |